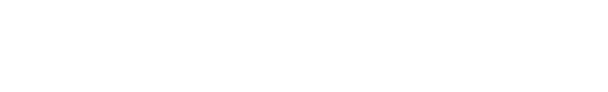About Us事務所概要
Basic Philosophy事務所理念
「経済の法務パートナー」として
当事務所は創設以来一貫して、自己責任・自己判断の時代における最先端の法律事務所として、
企業法務・金融法務を中心に、企業危機管理及び企業コンプライアンスの確立に努めるとともに、
「経済の法務パートナー」を目指し、顧問先・依頼者の皆様が各種企業活動を展開するために
必要な幅広い法務サービスを提供し、「虎中」(とらちゅう)の愛称でご支持を載いて参りました。
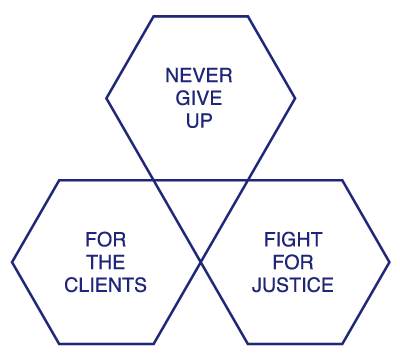
当事務所は、「 FOR THE CLIENTS 」、「 NEVER GIVE UP 」、「 FIGHT FOR JUSTICE 」のポリシーのもと、
顧問先・クライアントの皆様のご依頼・ご期待にお応えするために全員一丸となり、日々業務に取り組んでいます。
History沿革

- 1983年
- 「今井和男法律事務所」として台東区にて開業
- 1992年
- 「虎門中央法律事務所」に改称するとともに港区西新橋二丁目に事務所移転
- 1996年
- 港区虎ノ門一丁目に事務所移転
- 2006年
- 港区西新橋一丁目に事務所移転
- 2014年
- 虎門中央法律事務所 世澤外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業)を開始
苗村法律事務所(大阪・東京)と統合
- 2015年
- 港区虎ノ門一丁目(現所在地)に事務所移転
- 2016年
- 苗村法律事務所(大阪・東京)との統合を解消し新たな提携関係へ移行
- 2020年
- 安理律師事務所と提携を開始
共同事業の名称を、「虎門中央法律事務所 安理外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業)」に変更
Global Networkグローバルネットワーク
当事務所の有するグローバルネットワークを活用し、クライアントの皆様のクロスボーダー取引、海外投資・進出、海外子会社のリスク管理における法的助言を行っております。
安理外国法事務弁護士事務所との外国法共同事業について
当事務所は、中国の安理律師事務所を母体とする安理外国法事務弁護士事務所と外国法共同事業を実施しております。安理律師事務所は、北京、上海、深?をはじめ13の都市に拠点を有し、100名以上のパートナーと500名を超える法律専門スタッフを擁する総合法律事務所であり、日本企業の中国進出・撤退、中国企業とのアライアンス等の中国関連案件において高いプレゼンスを有しております。
世界各国の法律事務所とのネットワークについて
当事務所は、上記外国法共同事業のほか、国内外の依頼者による海外における事業展開を支援すべく、国外の法律事務所とのネットワークの拡充に努めております。特に、香港、台湾、韓国、フランスにかかる案件につきましては、「 FOR THE CLIENTS 」、「 NEVER GIVE UP 」、「 FIGHT FOR JUSTICE 」の理念を共有する優れた法律事務所と協働する態勢を構築しております。また、その他の各国(例として、シンガポール、タイ、インドネシア、ベトナム、インド、イギリス、ドイツ、ニュージーランド、カナダ、アメリカハワイ州など)にかかる案件につきましても、問題の内容、性質等に応じて現地の法律事務所と連携することにより、依頼者に最適なソリューションを提供するよう努めております。
Our Accomplishments主な実績
当事務所がこれまでに担当した訴訟事件は膨大な数に上りますが、これらのうち先例的価値が高いとして判例誌等の公刊物に取り上げられたものも多数存在します。下記はその一例ですが、常に受任事件について、「事件」のスジとスワリを見極め、依頼者利益の最大化・極大化を図るために柔軟・迅速な対応を旨としています。
- 損害賠償請求事件
前橋地裁高崎支部(判決日 平成31年1月10日) - 雑誌名
- 判例時報2434号36頁(判例時報社)
本件は、被告(Y)の不法行為(本事件)によりX及びその被相続人に生じた損害につき、不法行為時から20年経過した後に、XがYに対して損害賠償請求訴訟を提起した事案である。Yは本事件後に行方不明となっており、期日に出頭せず、また何らの答弁をしていないが、除斥期間は裁判所による職権適用が可能であるため①民法724条後段の除斥期間による請求権を保存するために必要な行為は何か、②所在不明者に対する通知につき、宛て所に尋ね当たらないとして返送されたものであってもYに到達したと扱ってよいかが争点となった。
本判決は、①については、除斥期間の満了までに裁判上の権利行使を行う必要まではなく、裁判外で権利行使の意思を明確にすれば足りるとした。また、②については、Yが本事件に及んだ上で逃亡していること、敢えて住民票上の住所を移転していないなどといった本件事情の下では、Yが不利益を甘受すべきであるとして、住民票から判明する最後の住所地に宛てた郵便物についてYの了知可能な状態に客観的に置かれたとして、Yへの到達を認めた。宛て所尋ね当たらずであっても意思表示の到達を認めた点が限界的事例判断として実務上の参考に値する。
- 保険契約者地位確認請求控訴事件
広島高等裁判所岡山支部(判決日 平成30年3月22日) - 雑誌名
- 金融法務事情2090号70頁(金融財政事情研究会)
金融・商事判例1546号33頁(経済法令研究会)
判例時報2387号(判例時報社)
本判決は、保険会社が、X社との間の保険契約について、その受取人であり同社の代表者である人物が保険約款上の重大事由解除条項に規定された「反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること」(以下「本件暴排条項」という)に該当するとして同契約を解除したところ、X社が①本件暴排条項は保険法30条、同57条の趣旨に鑑みて保険金不正請求を招来する高い蓋然性がある場合に限り適用されなければならない、また②その代表者は「社会的に非難されるべき関係を有している」には該当しないと主張し、解除の有効性を争った事件について下されたものである。保険約款に導入された暴力団排除条項については、保険法における重大事由解除の規律に抵触するとして、その有効性に疑義を呈する見解があるところ、本判決はこの点に異論を差し挟むことなく、X社の上記①の主張を排斥して、本件暴排条項に基づく解除を有効と認めている。本判決は、暴力団排除条項と保険法の規律に関する初めての司法判断であり、内容において保険暴排を推進する先例として大きな意義を有する。また、本判決においては、上記②の主張に関しては、「社会的に非難されるべき関係」について、新たに「反社会的勢力との関係を積極的に誇示する」といった例示をした上で、X社の代表者がこれに該当すると認定しており、この点は保険分野以外の領域においても、暴力団周辺者の排除を一層推進するものと期待されるところである。
- 否認権行使請求事件
東京地方裁判所(判決日 平成30年2月27日) - 雑誌名
- 金融・商事判例1542号45頁(経済法令研究会)
金融法務事情2098号78頁(金融財政事情研究会)
本件は、破産会社の破産管財人であるXが、破産会社が破産手続開始前にYに対して行った支払について、破産会社が支払不能になった後にされた行為、又は破産会社が支払不能になる前30日以内にされその時期が破産者の義務に属しない行為であるとして、否認権を行使し、Yに対し、当該支払に係る金員及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
本判決において判断された争点は、当該支払当時破産会社が支払不能であったか否かという点であり、本裁判例は支払不能該当性について事実認定の一助となるものである。特に、「債務者が無理算段をしているような場合、すなわち全く返済の見込みの立たない借入れや商品の投げ売り等によって資金を調達して延命を図っているような状態にある場合」(高松高判H26.5.23金法2027号52頁)には支払不能に該当するという裁判例等が存在するところ、どこまでの事情が存在すれば「債務者が無理算段をしている」といえるかという点につき、消極の一事例を加えるものといえる。
- 再生債権査定申立事件
東京地方裁判所(決定日 平成29年1月30日) - 雑誌名
- 金融法務事情2070号88頁(金融財政事情研究会)
民事再生手続中、再生債務者が裁判所の許可(民事再生法85条の2)を得て実行した相殺に対し、再生債権者たる金融機関の立場で、同相殺には理由が無い旨主張して再生債権査定申立てを行ったところ、再生債権者の主張が認められた事例である。同再生債務者は、いわゆる通貨オプション取引に際して、同金融機関側に優越的地位の濫用、適合性原則違反及び説明義務違反等があったとして、不法行為に基づく損害賠償請求権を有する旨主張し、上記相殺に基づいて金融機関側の再生債権届出に対して異議を述べた。本決定では、再生債務者の主張には何れも理由が無い旨を明確に認定し、相殺を否定して、金融機関の届出債権全額を認めている。本件は、通貨オプション等のデリバティブ取引に係る不法行為の成否が非訟手続において問題となっており、その判断に際して訴訟手続と同じ枠組みが用いられている点に特徴がある。また、再生債務者による相殺(民事再生法85条の2)に係る裁判所の許可手続に際しては、条文上、債権者側に異議申立ての機会が保障されていないところ、本件では、査定手続を通じて実質的にこの機会が保障されている。
- 補償金請求事件
東京地方裁判所(判決日 平成29年11月29日) - 雑誌名
- 金融法務事情2094号78頁(金融財政事情研究会)
本件は、海外ATMで現地通貨を引き出すことができる国際ブランドと提携したデビットカードとしての機能が付帯されたキャッシュカードにつき、第三者が無断で当該カードのデビットカード機能を用いて海外ATMで不正に現地通貨を引き出したため、預金者本人の預金残高が減った場合に、いわゆる預金者保護法4条1項が直接又は類推適用されるかが争われた事案である。預金者は、デビットカードを利用した海外ATMでの現地通貨引き出しの仕組みは預金者保護法に定める「預貯金の払戻し等」に該当するとして、カード発行会社である銀行に対し同法に基づく補償金の支払いを求めたが、裁判所は、デビットカードを利用した取引は、預貯金の払戻し等に該当しないため預金者保護法は直接適用されず、また、デビットカードを利用した取引と預貯金の払戻し等では重要な相違が複数あることや法の趣旨から類推適用もされないと判じた。以上のとおり、国際ブランドと提携したデビットカード機能を利用した海外ATMでの現地通貨の不正な引き出し行為が、預金者保護法の保護の対象外であることを判断したものであり、金融実務に対して重要な意義を与えた裁判例である。
-
預金契約解約無効確認請求控訴事件
福岡高等裁判所(判決日 平成28年10月4日) - 雑誌名
- 金融・商事判例1504号24頁(経済法令研究会)
金融法務事情2052号90頁(金融財政事情研究会)
本件は高裁で初めて、①銀行の預金取引約款の暴力団排除条項の有効性、②預金契約締結後に普通預金約款に追加された暴力団排除条項に基づく預金契約の解除の有効性につき、いずれも肯定した裁判例である。判決のなかで、銀行が普通預金取引約款に定めた暴力団排除条項は、憲法14条1項、22条1項の趣旨に反するものではなく、公序良俗に反するものでもなく有効であること、銀行が既存の預金契約に暴力団排除条項を追加することについては、合理的な取引約款の変更に当たる場合には、既存顧客との個別の合意がなくとも預金契約に変更の効力が及ぶと判断された。いわゆる約款取引における遡及適用について裁判例も限られるなかで、遡及適用につき判断したという点においても意義の大きい判決である。
- 普通預金口座取引解約無効確認請求事件
東京地方裁判所(判決日 平成28年5月18日) - 雑誌名
- 金融・商事判例1497号56頁(経済法令研究会)
金融法務事情2050号77頁(金融財政事情研究会)
本件は、銀行の暴力団排除条項に基づく預金契約の解除の有効性につき、口座の利用目的にかかわらず有効であると判断した初めての裁判例である。本判決では、①約款である普通預金規定に反社会的勢力排除規定が追加され変更される前に締結された預金契約についても、反社会的勢力排除条項を適用し解除することができるか、②預金口座の利用目的がどのようなものであるかにかかわらず、反社会的勢力に属する者の預金契約に反社排除規定の適用があるかについて、いずれも有効であると判断された。近時の金融機関における暴力団排除の機運の高まりのなかで、金融機関の反社会的勢力排除の実務の参考になる裁判例である。
- 預金契約解約無効確認請求事件
福岡地方裁判所(判決日 平成28年3月4日) - 雑誌名
- 金融・商事判例1490号44頁(経済法令研究会)
金融法務事情2038号94頁(金融財政事情研究会)
本判決は、暴力団排除条項の不利益変更(いわゆる遡及適用)につき、初めてこれを認める判断をした、金融実務に大きな影響を及ぼす判決である。事案としては、指定暴力団幹部が銀行に対し、暴力団排除条項による預金解約は無効であるとして、暴力団排除条項の有効性、預金取引約款の変更(暴力団排除条項のいわゆる遡及適用)の効力等について争ったもので、本判決は預金取引約款の変更を認め原告らの請求を棄却した。約款の不利益変更については裁判例の蓄積も十分にあるとは言えず、暴力団排除条項の遡及適用についても金融機関の対応が分かれていたなかでの初めての判決という意味で、反社対応において大きな意味を有する判決である。
- 価格変更等請求控訴事件
東京高等裁判所(判決日 平成27年11月19日) (原審判決日 平成27年6月26日) - 雑誌名
- 季刊不動産研究第58巻第4号107頁(日本不動産研究所)
都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において、同法71条3項によるいわゆる地区外転出の申出をした借家権者に対する同法91条1項に基づく対価補償の価額について、建築物の価額に対する一般的な借家権の価額の割合を乗じて算出する方法(いわゆる割合法)によるべきである旨の借家権者の主張を排斥し、当該再開発事業の施行地区付近において借家権の取引価格が成立していると認めるに足りない事情の下においては、当該借家権の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決は適法であるとされた事例である。
本裁判例は、財産的価値が稀薄な借家権について、都市再開発法91条補償の要否と借家権価格を判断したものであり、内容も理路整然としており、今後、同様の事案に対して参考になるものである。
- 請負工事履行請求事件 / 損害賠償請求事件 / 違約金請求事件
東京地方裁判所(判決日 平成24年12月21日) - 雑誌名
- 金融・商事判例1421号48頁(経済法令研究会)
本件は、建設会社が暴力団の密接交際者と締結した建物建築請負契約につき、密接交際者が建設会社に対し建築建設工事の実施を求めたが、建設会社が動機の錯誤等を主張し、錯誤無効が認められた事案である。契約当時、建設会社が注文者を密接交際者と知っていれば契約を締結することはなかったという動機の表示を黙示の表示という態様で認め、密接交際者という属性についても、暴力団員と便宜を供与し共生する事情を指摘し、社会的に非難されるべき関係にあるとしてこれを認めた。昨今、契約書に反社会的勢力排除条項を導入するのが一般的になってきているが、反社排除条項が導入されていないような場合の関係解消の実例、密接交際者の意義を明らかにしたといった点で、反社会的勢力排除というコンプライアンスの実践に参考になる事案である。
- 不当利得返還請求事件
最高裁判所(判決日 平成23年12月15日) - 雑誌名
- 金融法務事情1937号4頁(金融財政事情研究会)
金融・商事判例1382号12頁(経済法令研究会)
NBL969号4頁(商事法務)
判例時報2138号37頁(判例時報社)
判例タイムズ1364号78頁(判例タイムズ社)
本件は、銀行が融資先のA会社から約束手形の取立委任を受けたところ、その後、A会社が民事再生手続を開始したため銀行に対する借入金につき期限の利益を喪失し、銀行は取立委任を受けた約束手形について商事留置権を有していたという事案において、銀行が、A会社との間で締結した銀行取引約定(銀行が担保及び占有している手形等については法定の手続によらずに取立て等による取得金を債務の弁済に充当し得る旨の定めがある)に基づき、A会社の民事再生手続開始後に取り立てた約束手形の取立金をA会社の債務に充当することを認めた初の最高裁判例である。破産手続においては同様の事案に関する判例は存在していたところ、民事再生手続における判例は存在しておらず実務における対応が分かれていたが、本判例により、民事再生手続においても、商事留置権による約束手形の取立金の留置が認められることや銀行による弁済充当を認めた銀行取引約定が効力を有することについて最高裁の判断が初めて示されることになり、金融実務や再生実務に対して重要な意義を与えた判例である。
- 担保不動産競売手続取消決定に対する執行抗告事件
東京高等裁判所(判決日 平成22年9月9日) - 雑誌名
- 金融法務事情1912号95頁(金融財政事情研究会)
建物建築工事請負代金債権を被担保債権とする商事留置権が成立することを前提に決定された買受可能価額に基づく無剰余であるとして担保不動産競売手続を取り消した決定に対する執行抗告において商事留置権は成立しないとして原決定が取り消された事例である。
- 違約金請求事件
東京地方裁判所(判決日 平成21年10月16日) - 雑誌名
- 判例タイムズ1350号199頁(判例タイムズ社)
訴外A社に不動産を売却した原告が、債務不履行(代金不払)による契約解除を主張して、A社の買主たる地位を承継した被告に対し違約金の支払いを求めたのに対し、被告から、原告に対し、同売買契約は原告の解除以前に被告が手付金を放棄して解除済みであったとして、手付金と別途支払済の中間金の支払を求める反訴が提起された事案である。
- 売掛代金請求事件
東京地方裁判所(判決日 平成21年6月17日) - 雑誌名
- 判例タイムズ1310号150頁(判例タイムズ社)
本件は、被告(Y)の社長秘書が、原告(X)との間で、Y名義を使用して、8か月余りの間に総額57億円にも及ぶ大量の新幹線回数券等の売買取引を行っていたところ、XからYに対し、そのうち未払代金相当額として8億2900万円余りの請求がなされた事案である。Xは、①社長秘書に代理権が存在し又は表見代理が成立することを前提に、XY間に売買契約が成立する、②社長秘書の不法行為が業務の執行につきなされており、Yに民法715条の使用者責任が存在する、と主張したが、裁判所は、社長秘書に職務権限は認められず、取引総額が57億円に及ぶなど取引に不自然な点が多数存在しており、Yは社長秘書に職務権限がないことを容易に知り得たと認定し、Xに表見代理の「正当事由」はなく、また社長秘書に職務権限がないことを知らなかったことにつき重大な過失があるとして使用者責任も否定した。
本件は、民法715条の使用者責任に関して、相手方に重過失の存在を認めた数少ない裁判例の一つであり、東京地裁平18・10・27判決(下記ご参照)とともに実務上参考になる事例である。
- 賃金請求控訴事件
東京高等裁判所(判決日 平成19年10月30日) - 雑誌名
- 労働判例963号54頁(産労総合研究所)
本件は、Y社が改正高年齢者雇用安定法の施行に伴い、定年を55歳から60歳に引き上げ、併せて55歳に達した 翌日から嘱託社員として55歳以下の従業員とは別の給与規程を作成し、これをXらに適用したところ、かかる規程は就業規則の不利益変更に当たるとして、Xらが「本来支給されるべき賃金」との差額等の支払を請求 した事案である。
一審及び控訴審をとおして争点は、①本件就業規則の変更は不利益変更か、②本件就業規則の変更に合理性はあるかであった。一審は①について否定することなく、②について就業規則不利益変更法理に関する一連の判例を引用し、Y社が本件就業規則の変更をすることには合理性があると結論づけた。一方控訴審の判決はこれとは異なり、①について不利益変更該当性を明確に否定したものである。控訴審判決は進んで、新就業規則の内容は、当事者らの置かれていた具体的な状況の中で、労働契約を規律する雇用関係についての私法秩序に適合しており、法規範性を認めるための合理的な労働条件を定めているもので、必要最小限の合理性があったとした。
同種の事案で、問題となった就業規則の変更が不利益変更に当たらず、就業規則不利益変更法理の適用もないと判示した裁判例は少なく、さらに使用者と労働者との間の雇用関係を規律する労働条件の法的規範性について、必要最小限の合理性という判断基準を提示した点において実務上意義があると思料する。
-
売買代金請求事件
東京地方裁判所(判決日 平成18年10月27日) - 雑誌名
- 判例時報1972号96頁(判例時報社)
本件は、旅行代理店である原告(X)が、旅行鞄の販売等を目的とする会社である被告(Y)の従業員と、平成15年から1年3か月余りの間、Y名義で総額6億円を超える新幹線回数券の売買を行っていたところ、うち1億1000万円余りの支払いがなされなかったとして、①XY間の売買契約の成立、②表見代理の成立、③使用者責任、の主張 をして、Yに対し未払金の請求をした事案であり、使用者責任の成否が主な争点となった。
詳細は判決文に譲るが、裁判所は、Xが僅かな注意を払いさえすれば適法な取引でないことを知ることが できたのに漫然と取引を継続した等としてXに故意に準ずる程度の注意の欠缺があるとした上で、Xに保護を与える とすると、自らの重大な不注意によりYに不利益を生じさせ、そのことによって一方的に利益を得るという著しく不当な結果になり、公平の見地上、Xに全く保護を与えないことが相当と認められるとして、Xに重過失の存在を認め、Yの使用者責任を否定した。
民法715条の使用者責任に関して、相手方に重過失の存在を認めた裁判例は少なく、実務上参考になる事例といえる。
- 保険金請求事件
東京地方裁判所(判決日 平成17年3月4日) - 雑誌名
- 判例タイムズ1219号292頁(判例タイムズ社)
生命保険契約の災害割増特約及び傷害特約においては「不慮の事故」を直接の原因として保険事故が発生した 場合、死亡保険金等を支払う旨規定している。
本件は、急性心筋梗塞等と診断された被保険者が心臓手術を受け集中治療室で経過観察中に、経過観察のため装着された治療器具から大量出血し死亡したことが、上記「不慮の事故」にあたるとして生命保険会社に 保険金請求がなされた事案である。
判決は約款上疾病の診断・治療を目的とした医師の診療上の行為が不慮の事故から除外されている点について、原則として保険事故としての傷害を基礎に置く診療行為に関して発生した患者事故については保険事故の対象とし、疾病に診断・治療を目的とした医師の診療上の行為から発生した患者事故については保険事故の対象から除外することを定めたものと言うべきと判示し、請求を棄却した。医療機関で発生した患者事故について不慮の事故に該当するか否かの基準を示した点に意義があると思料する。
- 保証債務履行等請求事件
東京地方裁判所(判決日 平成15年10月28日) - 雑誌名
- 金融・商事判例1183号6頁(経済法令研究会)
極度額110億円の連帯保証契約に基づく連帯保証債務履行請求について、不起訴合意、保証契約不成立、 通謀虚偽表示、心裡留保、錯誤、詐欺、信義則違反、権利濫用などの主張・抗弁をいずれも排斥し、全額の請求を認容するとともに、被保全権利である保証債務履行請求権の発生日と不動産売買契約日とが同日であっても、詐害行為当時すでに被保全権利成立の基礎たる事実が発生し近い将来においてその成立が高度の蓋然性をもって見込まれる場合、その見込みどおりに債権が成立したときは、この債権は詐害行為取消権の被保全権利となるとして不動産売買について詐害行為取消を認めた事例。
社会的に耳目を集めた事案の判決であるが、理論的には詐害行為取消権の被保全権利の発生時期についての判示が同種事案の参考になるものと思料する。
-
広告代金等請求控訴事件
東京高等裁判所(判決日 平成13年5月23日) - 雑誌名
- 判例時報1758号53頁(判例時報社)
本件は、新聞・書籍等を発行するXが、「広告予算申請書」と題する一見すると契約書とも見られる書面が存在することを根拠に、大手電機メーカーであるYとの間でX発刊の新聞等への広告掲載等の契約が存在するとして、Yに対し、同契約に基づき金552万円余りを請求し事案である。
当時、総会屋等に対する利益供与事件により総務担当者が逮捕される事件が次々に発生し、Yも総務担当者が 逮捕されたことを契機に総務部を窓口とする違法と考えられる全ての取引の絶縁作業を行っており、本件はまさにこのような絶縁作業の一貫に位置付けられる事案であった。
裁判所は、広告部ではなく総務担当者が交渉を行っていたなどXY間の交渉経過の特殊性や契約内容自体の不自然さなどにより、その支払いの実態は賛助金の支払(贈与)に過ぎないと認定し、「広告予算申請書」が交付 されたからといって広告掲載等の契約が成立したとは認められないとしてXの請求を棄却した。
なお、判決は傍論で、仮に契約の成立が認められるとしても、同契約は株主に対する利益供与と推定されるおそれがあるため公序良俗に反して無効になると認められる認定している。
本判決は、正常な取引を装った金員の請求について、契約書と見られる書面が交付されているにも関わらず、その請求を排斥した事案として実務上参考になる事例といえる。
- 換価代金等配当処分取消請求事件
東京地方裁判所(判決日 平成13年3月28日) - 雑誌名
- 判例時報1740号35頁(判例時報社)
金融機関が、債務者が出店しているテナントの入居保証金返還請求権(毎年償還する約定あり)について質権の設定を受け、第三債務者であるビルオーナーから確定日付ある承諾書の差し入れを受けていたところ、国税局が 債務者に対する滞納処分として保証金返還請求権を差押え、ビルオーナーから償還金を取り立てたものの、 配当処分において、①金融機関が質権を実行するために要求されている手続を履践しおらず、質権の効力が当該入居保証金償還金に及ばない、②ビルオーナーの承諾書の記載から被担保債権が特定できないなどとして 金融機関に対する配当をなしとしたため、配当処分の取消しを求めて訴訟を提起。
東京地裁は、承諾書の解釈として質権の効力が入居保証金償還金に及ぶとして①の理由による処分を取り消し、 ②については被担保債権が特定できないとして請求を棄却した。
事例判決ではあるが、換価配当処分についての裁判例の数少ない例である。
-
文書提出命令申立事件
東京地方裁判所(決定日 平成11年8月16日) - 雑誌名
- 金融法務事情1557号76頁(金融財政事情研究会)
銀行が行った融資について、債務者が融資判断の適法性を争い、銀行の貸出禀議書、元帳、担保評価書、 債権譲渡契約書等について、 文書提出命令の申立てを行った事案。
新民事訴訟法で改正された分野で当時は議論があったが、東京地裁は、貸出禀議書は自己使用文書に該当する、その余については必要性がないとして申立を却下した。
なお、貸出禀議書については、その後平成11年11月12日最高裁第二小法廷決定で、自己使用文書に該当するとの判断が示され、決着した。
-
供託還付金請求権確認請求控訴事件
東京高等裁判所(判決日 平成9年2月20日) - 雑誌名
- 判例タイムズ986号231頁(判例タイムズ社)
未発生の賃料債権について抵当権に基づく物上代位による差押えと債権譲渡とが競合した場合の優劣関係についての裁判例。
抵当権登記が債権譲渡通知よりも前に経由されていれば、物上代位による差押えが優先すると判示した。
その後、この論点については最判平10・1・30民集53巻1号1頁が、物上代位の目的となる債権が既に譲渡され、対抗要件を具備していても、抵当権者は自ら差し押さえて物上代位権を行使することができる旨判示し、決着を見た。